- 芸術文化日録(AtoCジャーナル)
戦後80年のメディア
2025年08月15日
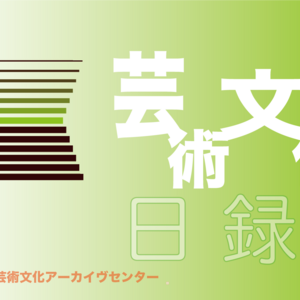
芸術文化日録の投稿が1ヶ月以上滞っておりました。申し訳ありません。8月15日分から再開します。空白期間もいずれ埋めていきたく。
戦後80年の8月15日は、当然ながら各メディアが大きな特集を組んだ。なかでも手厚かったのはNHK。いくつもの終戦関連番組を、15日を中心に立て続けに放送していた。一般市民の終戦前後の日記を集めて追体験し、外務大臣の手帳から解き明かす外交の経過などなど。部分的にしか観ていないが、開戦を前に彼我の経済力や工業力を緻密に分析して日米の戦争が「必敗」であると断じた「総力戦研究所」に光を当てた「シミュレーション 昭和16年 夏の敗戦」が秀逸だった。総理大臣をはじめ、閣僚への机上演習の説明では、ドイツの敗戦、南方戦線への物資輸送の破綻、本土空襲はもとより終末期にソ連が参戦するところまで予測していた。しかし、陸軍大臣の東條英樹は「実際の戦争と机上のお勉強は違う」と言い切り、精神力で日露戦争に勝ったと一蹴する。
片山杜秀が解説役となった「音楽はかつて“軍需品”だった 〜幻の楽譜に描かれた戦争〜」は、NHKに多数の楽譜が残っていた戦意高揚の音楽を紹介する企画。こういう番組でなければ聴くことができない、隠れた音楽史の教科書であった。
北海道新聞は、日本の無条件降伏が発表された8月15日の紙面を、現代の視点に基づいて書き換え、折り込み特集としたユニークな取り組み。「日本敗戦 無条件降伏」の大見出しは、終戦当時の実際の紙面では「聖断厳かに下り戦ひ局を結ぶ」。
「戦後80年に考える」と題した《各自核論》の吉見俊哉論考は興味深かった。トランプ政権のもとで、日本の新米感が下落していることに着目し、「離米」とアジアの多様性に寄り添う道を提唱している。