北海道芸術文化アーカイヴセンター | Hokkaido Arts and Culture Archives Center
Hokkaido Arts and Culture Archives Center北海道芸術文化アーカイヴセンター
北海道に関連する芸術・文化活動と資料・書籍の情報をアーカイブ(記録・保存)しています。
芸術・文化活動
266件資料・書籍
1172件ACAマガジン
561件
イベントや活動名、資料タイトル、キーワード、関連人物等で自由検索
最近アーカイブされた芸術・文化活動
2nd. International NOW MUSIC Festival Sapporo '87
公演, 1987年10月25日北海道のアーティスト50+4人展 FINAL
展覧会, 2026年1月31日梅津和時 D.U.B '87
公演, 1987年7月28日斎藤歩追悼 歩さんお別れの会
その他, 2025年11月7日アジアンジャズ・クリエイティブコンサートVol.1
公演, 2025年10月26日
最近アーカイブされた資料・書籍
蝦夷古地図物語
図書, 1974年12月10日札幌文学 95号
雑誌, 2025年8月20日札幌文学 93号 田中和夫追悼号
雑誌, 2023年9月30日札幌文学 94号
雑誌, 2024年8月20日札幌文学 92号
雑誌, 2022年8月20日
ACAマガジン
日々更新中の「AtoCジャーナル」、ACAからのご報告、ACA運営メンバーほかによるドキュメント(報告、エッセイ、批評、論考など)の更新情報を掲載しています。

fixed article
- お知らせ
2025.03.31
まずお読みください
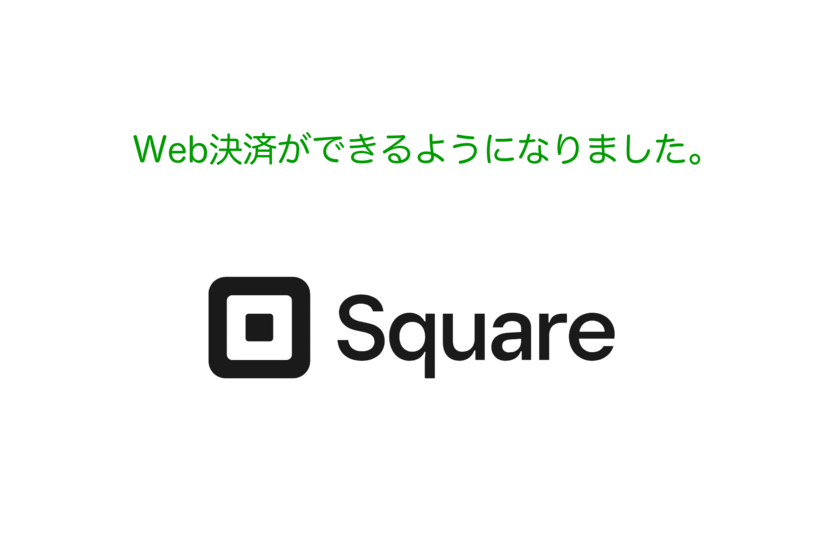
fixed article
- お知らせ
2026.01.09
賛助会員を募集しています

fixed article
- 読み物
2025.05.30
道内初の本格的郷土史デジタルアーカイブとその課題
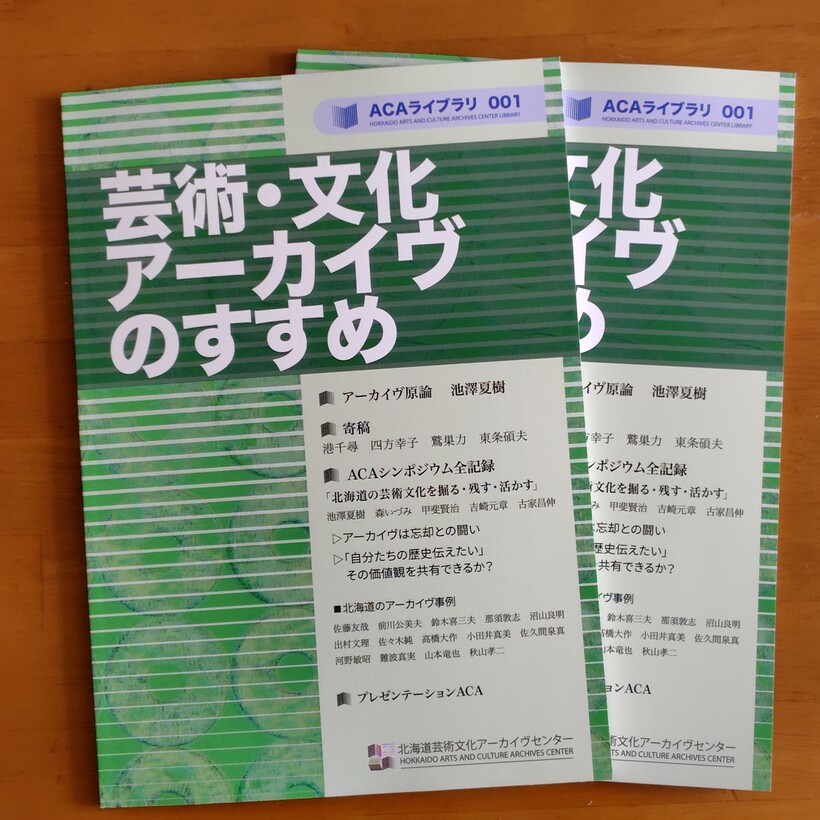
fixed article
- お知らせ
2025.05.07
《ACAライブラリ001》書店でも販売
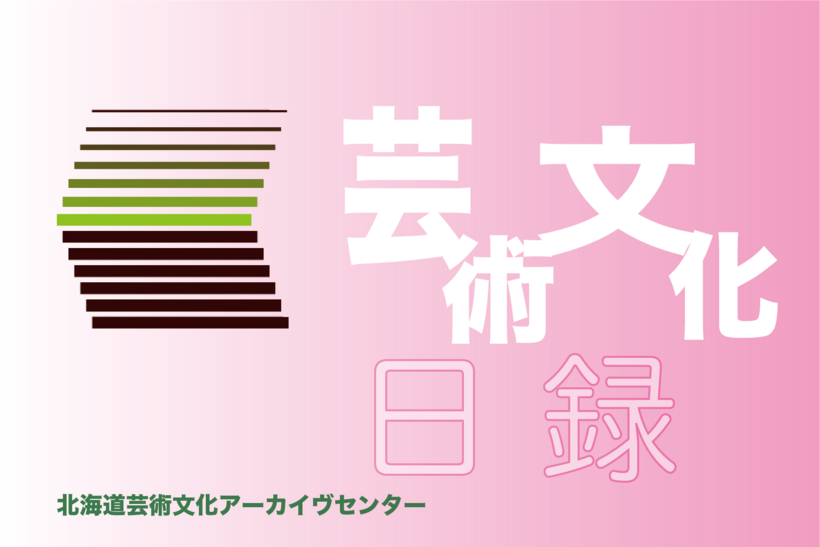
- 芸術文化日録(AtoCジャーナル)
2026.02.10
「文学館コレクションの輝き」展
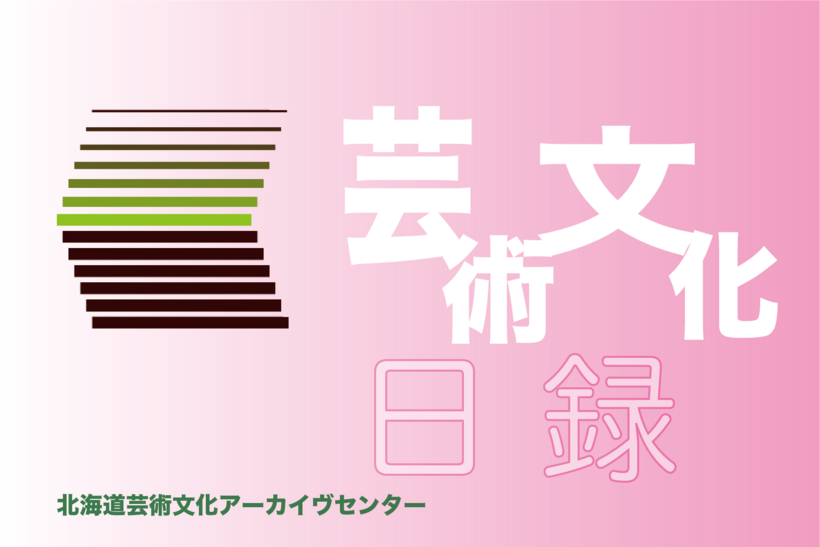
- 芸術文化日録(AtoCジャーナル)
2026.02.07
『北海道の生活史』刊行記念会見/北方領土記録集は復刊